ハローワークはいつも人でいっぱい!?
会社を辞めてしまった時、すでに次の再就職先が決まっていればいいのですが、そうでない場合はまずハローワークへ失業保険の手続きに行きます。
しかし私のように自己都合で辞めた場合は、会社都合の場合(たとえば倒産・解雇)と違って手続きしてもすぐには受給できません。
ここでは自身の経験談やそこから考えさせられたことを書いてみます。
世間の狭い田舎
私が初めて失業保険の手続きに行ったのは、地元田舎のハローワークでした。
田舎は意外と世間が狭いので、ハローワークでもし知っている人に会ったりでもしたらと思うと何か肩身の狭い、恥ずかしいような気分になりました。
幸い知り合いに会うことはありませんでしたが、就職率が高い田舎にもかかわらず結構人(失業者)がいることには驚きましたね。
しかし後日、失業認定日に行ったハローワークで見慣れた制服を着た女性(おそらく辞めた会社の本社の人)を見かけた時は「ドキっ!」としました。
実はその人は同期入社で私のことも知っているはず。
何の用事で来ていたのかは知りませんが、ちょっと複雑な気分でした(^_^;)
失業手当の条件は年々厳しくなる…
それから約5年後、再就職した会社を退職して再び失業保険の手続きに行くことになるのですが…
そこはもう一度スクールで学ぶために引っ越した、大都会にあるハローワークでした。
引っ越したばかりなのでそこで知り合いに会うことはまずありませんが、さすが人が多いだけあって毎日のように様々な年代の、たくさんの人が手続きに訪れていました。
そしていざ手続きを始めてみると、年々失業保険の受給者が増えているせいか前回受給した時より認定条件が厳しくなっていました。
給付を受けるには、積極的に求職活動をした実績がないと認定されなくなっていたんです。
おそらく「とりあえず貰えるものは貰っておこう」という甘い考えを起こさせないようにするためでしょう。
支給額にショックを受ける
失業保険が受給できる期間は人によって異なりますが、自己都合で辞めた私はいずれも3ヶ月間だけでした。
支給額は支払われた給与の額によって決まるのですが、2回目のときは前職より給与がずっと低かったため前回よりガクンと下がり、ちょっとショックでした。
その時、転職する時はもっと上のレベルを目指すべきだと痛感させられたのは言うまでもありません(^_^;)
しかし、基本的に優良企業は従業員の定着率もよくなかなか欠員が出ませんし、自分の経験だけでは売り込む自信がない場合もありますよね。
でもだからといってまた以前と変わらない所に行ったり、さらにレベルを下げることはなるべくやめた方がいいと思います。
失業中は勉強期間に!
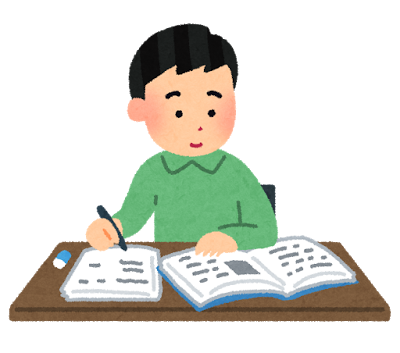
ハローワークに失業認定に行った時、応募した会社が少なかったりすると「どこでもいいから応募してください」と無責任なことを言われたりもします。
しかし、お金を稼ぐことだけを目的に適当に決めてしまった会社は、また嫌気がさして辞める可能性大なのは言うまでもないですよね。
私が今までの経験や友人知人たちが実行していた事から痛感させられたのは、どうしてもやりたいと思うことがあったら社会人スクール等で勉強すべきだということです。
これは養う家族がいる場合は難しいかもしれませんが、「人生を変えよう・上のレベルを目指そう」と思ったらやはり、それなりの努力も必要です。
楽に稼げる仕事はない
もちろん、勉強してきたからといってすぐに仕事を任せてもらえるものではないですが、その努力は認めてもらえますし就職活動の間口も確実に増えます。
やはり学生のアルバイトでも出来るような仕事では、いくら真面目に頑張ってもそれなりの収入しか得られない事が多いんです。
やっぱり失業している今だからこそ出来ることってあると思います。
仮に「まだ自分は若いから大丈夫」と思っていたとしても、5年後10年後に「あの時ちゃんと勉強しておけばよかった…」と悔やむ「あの時」というのは「今」です。
つまり過去の自分をつくったのも、未来の自分をつくるのも「今の自分」なんです。
働きながらの勉強は大変すぎる
実際、働きながら資格の勉強をするのは相当な覚悟がいります。
私の知り合いも働きながらスクールに通って勉強していましたが、仕事が忙しくて両立できず挫折していました。
スクールにはそんな、最初に高い授業料を納めたにもかかわらず途中で消えていく会社員もよくいますが…
正直、このパターンが一番人生の無駄(お金や時間の無駄)だと言えますね。
私の周りを見る限り、もしスクールに通うならなるべく時間のある失業中に、とにかく勉強に集中してしまった方が結果的には正解だと思います。
まとめ
ハローワークに行くと、想像以上に失業者や求職者がたくさん来ているかもしれません。
全員がライバルというわけではありませんが、世の中には仕事を求めてさまよっている人が多いことに驚きます。
ただ、同じ仕事をするならやはりレベルの高いところで自分のやりたい事をした方が労働意欲もわきますし、お金もちゃんとついてくるというものです。
今後について考えた時、自分が必要と思ったなら失業中にスクールで勉強するのもアリです。
もし「経済的にスクールは難しい…」という方はハローワークの職業訓練を利用する手もありますので、ご興味のある方は職業訓練・教育訓練制度の記事も参考にしてみてくださいね。
(関連記事)
